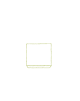防災意識を高める事業継続計画(Business Continuity Plan)訓練の実施報告(令和7年度)
皆さん、こんにちは!
包装資材事業部です。
毎年11月に実施しているBCP訓練。弊社はいつ大地震が起きてもおかしくない静岡県富士市に各拠点を置いているため、日頃から災害時における訓練に力を入れて、社員の防災意識を高めています。
今年は、11月7日に全社一斉で実施しました。
訓練は、各5拠点(紙器工場、木材工場、流通センター、港湾センター、住宅部)で行われ、その後、実際に消火器の使用や放水訓練も行いました。
1.訓練の目的:なぜ私たちは備えるのか?
私たちのBCP訓練は、「いかなる状況下でも事業活動を止めない」というお客様や社会に対する強いコミットメントの元に行っています。
今回の訓練は特に「人命の安全確保」と「最重要業務の迅速な復旧」という2つの柱に焦点を当てました。単に定められた手順を確認するようなものではなく、大地震やパンデミック、津波など様々な危機状況に柔軟に対応できるようにすることも重要と考えたからです。
まず、最優先すべきは社員の安全。そして、その安全が確保された上で、ビジネスの継続が遂行できる状態を確保することを訓練しました。被災によって当社が提供するサービスが一時的に停止するといった緊急時に、誰が・何を・どのような優先順位で実行するのかを明確にし、「いざ」という時に迷わず動ける組織体制を築くためのトレーニングがねらいです。
2.訓練の具体的な内容と想定シナリオ
今回の訓練では、具体的な自然災害、社会的な経済危機やパンデミックの状況を設定し、リアリティのある状況下での対応力を試みました。設定したシナリオは「交通網や電気系統に異常が出ない程度の地震の発生」です。
このシナリオに基づき、以下のようなアクションを集中的に訓練しました。
①初動対応と安否確認の迅速化
地震発生直後の通信インフラが制限された状況下で、全社員は安否確認システムを通じて地震の状況を報告いかに迅速に社員の安全を確認できるか検証しました。またこの訓練のポイントとして、連絡が取れない社員がいた場合、あらかじめ決めていた担当者が別の手段(SMS等)を用いてコンタクトを試みました。今回の訓練では、複数の連絡ルートを確保することの重要性を再認識できました。
②重要データの復旧と周辺状況の確認
各部署、各担当により二次災害や被災状況の確認を実施しました。
訓練でのポイントは時間目標「RTO:目標復旧時間」を設定したところです。手順書通りに状況確認できるかを計測しました。
(計測した確認事項)
・被災者(ケガ等)や火災などの迅速な発見
・必要に応じた機関への連絡
・事務所内に入れた場合は社内の設備・機器の状況や重要書類・データの持ち出しが可能かどうかの確認
・地域周辺の道路状況や近隣の様子の確認等
また、初期消火訓練も実施。新人社員を中心に消火器や放水ポンプを使って予行演習を行いました。訓練後に体験をした社員に話を聞いてみると、「消火器の使い方は社外でも使える知識なので、とても良い経験になりました。」という感想を貰いました。
③お客様および取引先への情報発信シュミレーション
危機発生時、お客様が最も不安に感じることは「情報がないこと」 です。
危機発生時、お客様が当社の状況が把握できず担当者と不通になることで不安に感じられることはできる限り避けたいところです。そのため 被害状況、サービスの停止範囲と復旧の見込み、当社の対応方針について、迅速かつ正確に得意先のお客様や外部の協力業者へ連絡する訓練を実施しました。
訓練でのポイントは、状況に応じた柔軟な対応、誤った情報や不確実な情報を発信しないことを厳格に守る訓練を行いました。
3.今回の訓練の振り返りと今後の課題
良かった点:「備え」の有効性を実感
今回の訓練では、特に事前の準備が功を奏した部分がありました。最新のBCPマニュアルは、役割分担と手順が明確化されていたため、多くの社員が迷いなく動くことができました。
今後の課題:「想定外」を乗り越えるための柔軟性
実際の現場では「想定外のトラブル」が発生する可能性は大いにあります。その際にマニュアルに頼りすぎずに、個々の社員が自律的に判断し行動していく能力が大事だと考えます。
今回の訓練によって、弊社における災害に対して自分たちで対処できることを体験することができました。それ以外に、消火器の放射時間は思ったより短いという実感は貴重な体験でした。
実践では当日の風向きや煙、炎を計算して距離を取るといった臨機応変な対応を求められることがとても大切だと感じました。消火器の位置など、改めて社内で確認したり、機会があれば社外時にも気を付けてみることを意識していこうと思いました。